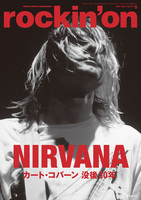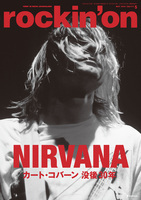pic by Kazumichi Kokei
pic by Kazumichi Kokei pic by Kazumichi Kokei
pic by Kazumichi Kokei pic by Kazumichi Kokei
pic by Kazumichi Kokei pic by Kazumichi Kokei
pic by Kazumichi Kokei pic by Kazumichi Kokei
pic by Kazumichi Kokei pic by Kazumichi Kokei
pic by Kazumichi Kokei pic by Kazumichi Kokei
pic by Kazumichi Kokeiライブは誰もが予想したとおり、「Holiday」でスタート。ステージ下手のロスタム・バドマングリがピコピコとキーボードを奏で、バックのクリス・トムソンが裏打ちのドラミングをキープし、ボトムを上手のベースのクリス・バイオがシメると、もうそれだけで「ヴァンパイア節」としか呼びようのない軽快なサウンドが目の前に現出する。そして、フロントに立つエズラ・クーニグが右手をせわしなく上下しながら、これまたさわやかな歌声を響かせると、コースト全体がポンピングしたみたいに「軽く」なっていく。
続く「White Sky」がまたふわふわと浮遊感を場内に満たしていく。エズラのヨーデルのようなミドル、その歌声をアフリカン・スタイルなコーラスが追いかける様が気持ちいい。3曲目からはファーストから「Cape Cod Kwassa Kwassa」で、そうなると、このバンドがまさにピーター・ガブリエルから継承した「白人によるアフロ・ポップの翻訳」サウンドがみるみる広がっていく。ピンスポットに照らされたエズラの独唱から、小刻みなロック・ビートへと走っていく「I Stand Corrected」、そして、一転バロック調のクラシック・フレーズを大胆に使った「M79」、きりもみ状態のギター・イントロが刺さりそうに飛んでくる「Bryn」、そして、セカンドに戻って性急なビートが駆け抜けていく「California English」「Cousins」の2連発へと経ていくと、このバンドが発明した「かぎりなく重量の消えていくソリッドなパンク・ポップ」がそこに現れていくのだ。
You Could Turn Your Back On The Bitter World――。「Cousins」の終盤、3回繰り返されるこのフレーズが、ヴァンパイア・ウィークエンドの「思想」だ。「この世の中がつらく厳しいのなら、背を向けることだってできる」。この一見現実逃避的な作法は、しかし、ヴァンパイア・ウィークエンドがただのパーティ・バンドであることを示すものではない。というか、むしろ、彼らを取り巻く現代的な窮屈さに抗うための、クレバーに選び抜かれた処世術なのである。
ヴァンパイア・ウィークエンドの詞を見ると、そこには音の快楽性とはまったく真逆に、非常にシリアスな時代認識とそこに生を受けた当事者の覚悟が語られていることに気づく。たとえばそれは、トム・ヨークが現代に感知しているこの世界の在り様と同じものであり、MGMTのアンドリューが当惑しながらサバイバルを決意した世界とシンクロするものでもあるだろう。そんな中にあって、ヴァンパイア・ウィークエンドが選択したものとは、つまり、「軽さ」なのである。トム・ヨークならばそれを悪魔との格闘と表現するシリアスさ、アンドリューならそれをコンプリケイテッドなサーフィンと表現するシリアスさ。それをヴァンパイア・ウィークエンドは、逃走という軽さをもって乗り越えようとする。だから、ヴァンパイア・ウィークエンドの音には、どこにも重さがない。そのような重さが引きずり込むシリアスさから逃れるための軽さ。そんな「利口さ」が、このバンドの「思想」であり、支持された最大の理由なのだ。もちろん、そのような逃走も、同様にシリアスであることは言うまでもないのだけど。
余談だが、前述の「M79」のときからそうだったのだけど、とにかくオーディエンスとのコミュニーケーションのとり方がうまいというか、実にこなれているのもヴァンパイア・ウィークエンドの特徴だ。これまでのインディー・ロック・バンドに支配的だった、相互排除的なステージとフロアの空気は、この新世代バンドには無縁だ。間奏のコーラスは事前にいったん観客に練習をさせ、演奏中は「はい、どうぞ!」と大きなゼスチャーで合図、曲そのものにオーディエンスを自然に巻き込んでいくエズラの姿は、ありそうでこれまでなかった新鮮な光景だった。
「A-Punk」での沸騰、「Giving Up The Gun」でのクライマックスを経て本チャンは55分、アンコールまで含めても1時間と15分くらいだったか、ヴァンパイア・ウィークエンドのパフォーマンスはそのアルバム同様あっという間に終わってしまった。それでも、ファーストからは全曲、セカンドからも8曲を演奏した。個人的には、セカンドの最終曲、「I Think Ur A Contra」を聞きたかった。この曲こそ、こんな世界をどんな風に愛すのか、そこで成り立つ複雑かつシンプルな2010年のラブ・ソングだと思っているので。(宮嵜広司)
セットリストは以下の通り。
1. Holiday
2. White Sky
3. Cape Cod Kwassa Kwassa
4. I Stand Corrected
5. M79
6. Bryn
7. California English
8. Cousins
9. Run
10. A-Punk
11. One(Blake’s Got A New Face)
12. The Kids Don’t Stand A Chance
13. Diplomat’s Son
14. Giving Up The Gun
15. Campus/Oxford Comma
Encore
16. Horchata
17. Boston
18. Mansard Roof
19. Walcott