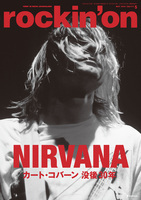自身の公演としては、初めての来日となった今回。ただし、このライブはアントニー・アンド・ザ・ジョンソンズではなく、アントニー・アンド・ザ・オーノズとして、である。最新作『THE CRYING LIGHT』を捧げた舞踏家、大野一雄の生誕地日本での公演を、アントニーは特別な夜にした。それが、「ライブ・パフォーマンスによるTHE CRYING LIGHT」ということである。つまりは、『THE CRYING LIGHT』がそうであったように、この夜は、この希代の舞踏家によって彼はどう救われたか、そのことを目の前で再現してみせるということになる。だから、この演出は、彼がどうしても辿らなければならない、不可避の道程なのである。
咳払いひとつが場の空気をかき乱してしまうほどの張り詰めた緊張感が会場を覆っている。ほとんど誰も喋っていない。中には靴を脱いでひざを折りたたむようにしたまま固まっている客もいる。もうなんか泣きそうになっている客もいる。なんなんだこれは。ブザーが鳴って、陰アナがもうすぐ開演することを告げる。だんだんと暗転していく。こんな始まりは、普段行くロックのライブでは、ない。
シンとした暗闇にぼうっと光が点る。舞台全面を覆うスクリーンに映像が映し出される。モノクロの映像は、白光した太陽だ。雲の間を、太陽はまるで駆け上るようにギラギラと強い光を放ち続けている。スクリーンの向こうでは、ウイリアム・バシンスキーがノイズを放出している。すると、そこにジョアンナ・コンスタンティンが登場する。鳥の口ばしのような形状のメタリックな面をつけ、まさしく鳥のように踊る。というか、動く。やがて、彼女は面をとり、まとっていた白布を脱ぐ。中から、肉体が出てくる。そして、喜びを表すように、踊る。というか、動く。誕生のようである。やがて、その肉体は、去り、再び現われたときには、頭から黒い布のようなものに覆われてしまっていた。その一連の流れは、まるで天から落ちてきた人間の道程である。われわれの聖性と汚れ、生と死、その単純にして圧倒的な宇宙の理が、簡潔に現出する。われわれはこれから、そのような「淵」に立つことを告げられるのである。そこにすまう魂に向き合うのである。
ジョアンナが去ると、スクリーンに映し出されたのは、接写されたひとの皮膚だった。ひび割れ、ところどころに毛が生えた、そのようなものが、宇宙の壮大な複雑さといとも軽々と繋がっていく。そして、それが、大野一雄のものであることが見えてくる。そこからは、彼のさまざまな姿だ。天空を見上げた全身。苦しそうに折り曲げられた手足。見ているだけで痛みの伝わるほど突っ張った指先。そのようなものが次々と映し出される。そして、それは、もう綺麗なのである。彼の舞踏の映像でもそうだけど、どの一瞬を切り取っても、大野一雄の姿かたちは美しい。そして、猛烈に哀しい。それは、天と地の狭間に生きとし生けるものすべての宿命である。そのどこにもいけない魂に、向き合う。
そして、スクリーンはようやく解かれる。現われたのは、一台のグランド・ピアノ。そこには、アントニーが座っていた。下手には、ジョンソンズからロブ・ムース。ヴァイオリンとアコースティック・ギター。そして、アントニーが歌いだしたのは、『THE CRYING LIGHT』の1曲目に収められている「Her Eyes Are Underneath The Ground」。
一瞬、空気がどうかしてしてしまったかと思う。なんという歌声だろう。そう、なんという歌声なのだろうかこれは。近い。目の前どころではない。肩を抱かれ、耳元で優しく、そして力強く響かせているような声。凄まじい。すべてが表現され、すべてが包み込まれ、そして、すべてが昇華されてしまったような、そのような歌声は、こんな言葉に捧げられる。誰も今、貴方を止めることなんてできない――。
このライブは、大野一雄の不在、である。ここにいない彼の、しかしながら強烈に残された痕跡に手向けられた賛美と憧れと感謝と、そして忘れてならないのは、われわれもまた、そのような「淵」で「どこにも行けない」魂が「止まることのない」生を生きている=踊っているという事実、である。
一雄の息子である大野慶人(といっても御年71歳だ)が、アントニーの歌声を拾いながら、踊る。ときにはバラの花を一輪掲げながら、あるいは、馬のような様態の巨大な被り物をつけながら。その折なす空間は、まさに「淵」である。だから、痛みがあり、哀しみがあり、しかし、喜びがある。聖と俗、生と死を行き交いながら、魂が鎮められていく。たとえばそこでは、アントニー自身の生の苦難すら、浄化されていくのだ(それは、「My Lady Story」の際、大野慶人が観客に向けた鏡の演出に見て取れた)。
「You Are My Sister」「Epilepsy Is Dancing」「Another World」などが披露された後、「The Crying Light」によって、この章は終わる。暗闇にいる赤子のように、貴方を想うためにわたしは生まれてきた――。人は、自分と同じような現実を、自分には到底できないような仕方で生き抜いている人を見つけ想うことでしか、生きることができない。というか、そのような存在について歌うことしか、できない。しかし、それを見つけた人は、それだけで幸せである。16歳のアントニーと、その彼がたまたま見かけたポスターに映っていた大野一雄の姿とは、そういうことだった。
ふたたびスクリーンが舞台を覆う。そこには、あの有名な『O氏の死者の書』の映像がかかる。豚の乳房を無邪気に吸う大野一雄がいる。スクリーンが取り払われる。大野慶人が大野一雄の指人形を操りながら舞台に登場する。アントニーが最後に歌ったのは、エルヴィス・プレスリーの「好きにならずにいられない」だった。
そして、ここで初めて、客席から万来の拍手が起こった。鳴り止まない拍手だった。
その拍手の中、アントニーはアンコールを歌った。曲は、「Hope There’s Someone」だった。
すべてが終わり、ふたたび大きな拍手が沸き起こる中、この舞台を生きたすべての演者が挨拶をする。アントニーが笑っている。大野慶人に花束を渡す。大野慶人もアントニーに花束を渡す。その花を千切って、アントニーは、慶人の手に収まっている大野一雄の人形に、花びらを何度も何度も降らせていた。(宮嵜広司)
アントニー・アンド・ザ・オーノズ @ 赤坂草月ホール
2010.02.12