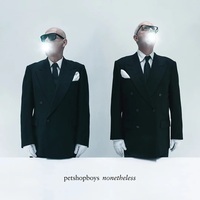昨年アメリカでアルバム・セールス通年2位を記録した『ヴューズ』に続くドレイクの新作、『More Life』が発売された。
発売以後、収録曲全22曲がBillboard ホットチャート100にランクイン、リリースから24時間で8990万回の再生回数を記録しアップル・ミュージックの1日の最多再生回数記録を更新、2位以下に4倍以上の差を付けて全米アルバム・チャート初登場1位など、様々な記録を更新している。
今最大の話題である『More Life』の収録曲全22曲を徹底的に解説する。ぜひ『More Life』を聴きながら読んでほしい。
まずは1曲目から11曲目の解説を前編としてお届けする。
ドレイク自身のインスタグラムで公開されている画像はこちら。
1. Free Smoke
冒頭を飾るこの曲は最初期からドレイクを支えてきたBoi-1daをプロデューサーに迎えたトラックになっていて、前作と対照的にドレイクのエッジを際立て、見せつける楽曲となっている。
冒頭のサンプリングのソウルフルなヴォーカルはオーストラリアのR&Bグループであるハイエイタス・カイヨーテのもの。その強烈な印象と続くトラックのビートの強靭さはこの曲のヒップホップとしての「真っ当さ」をよく表現している。
ドレイクのラップは定番の俺様節だが、テーマは自分に対するさまざまなディスへの対決表明となっている。かつてリル・ウェインのツアーバスの床で寝ていた自分が今やヒップホップ界の頂点を極めていることを見せつけつつ、自分のことを貶める連中についてはすべて黙らせると宣言している。
タイトルの「スモーク」は拳銃の煙のことで相手を撃ち殺す意味になるが、「フリー・スモーク」とはドレイクの造語で「売られた喧嘩は買うし必ず相手も黙らせてやる」という意味。
2. No Long Talk
2曲目もヒップホップ・アーティストとしての自負を叩きつけるトラック。プロデューサーは同郷トロント近郊出身の若手、マーダー・ビーツを迎えたもの。
いかにもドレイク好みなミニマムでエレクトロニックなビートを軸に、トロントの最高峰にいる自身と自身の抱えるOVOレーベルのアーティストらの俺様節を繰り広げるものになっているが、重要なのはここでイギリスのMCであるギグスが客演していること。
例えばこの曲の前半のドレイクのリリックはイギリス独特のスラングやカリブ系のスラングが散りばめてあり、後半のギグスはもちろんイギリス特有なMCとなっている。
もともとドレイクの出身地であるトロントはカリブ系の移民も多く、イギリス同様、カリブ系のカルチャーとの親和性が高いし、ある意味、ここでドレイクが打ち出しているのはアンチ・アメリカでもあるのだ。
あるいはアンチとまでは言わなくても、アメリカ人のヒップホップ・アーティストにはやりにくいことを意識的にかましてきているわけで、今回のアルバムでイギリスのアーティストが多く客演しているのはそういう理由からだろう。
タイトルもイギリス特有の言い回しで「long talker」、つまり、「話が長くてまだるっこしいばか」をもじったもので、自分たちはそうではなくてむしろ相手がそうだと警告するもの。
3. Passionfruit
かなり強気なヒップホップ芸を冒頭で繰り出したその続きはいきなり、カリビアン・リズムをフィーチャーした完璧なポップ・チューンである。
こんな音を自らのエスニック・バックグラウンドと繋がるものとして鳴らせる人はそうそうアメリカにはいないはずだ。
ここでプロデューサーを務めているのはイギリスのナナ・ローグス。内容は時間と場所にいつも拘束されていることからどうしても相手との関係が壊れていく心境を歌うという、人間関係ドラマもの。
どこまでも甘く、なおかつ憂いをたたえたメロディを歌い上げるドレイクのこの芸風はとにかく迫力がある。どうしてこれとさっきまでの高圧的なMCが同居することが可能なのか。
ドレイクはもちろん自分がヒップホップ・アーティストとして有名になったことは理解している。しかし普通に人生を生きていれば、一人の人間が悩むのはこういう局面ではないのか。だとしたら、こんな感情はラップで綴るよりもこういう風に歌い上げるしかないのではないか。
そんなあまりにも普通なアンビバレンツをこの曲は打ち出している。ひいてはこれこそがこのアルバムのテーマなのだ。しかも「会いたいけど会えない」というもどかしさをひとつの情感としてここまで甘酸っぱいものとして凝縮して、それをパッションフルーツと名付ける力業に、ここまでやるかと畏れ入った。
それをやるかやるないか。それがこのアルバムの聴きどころなのだ。
4. Jorja Interlude
続いてはプロデューサーであるNoah "40" Shebibのトラックにイギリスのヴォーカリスト、ジョージャ・スミスをフィーチャーした短い作品。
ジョージャはドレイクがイギリスをツアーした際にサポートを務めたのが縁でコラボレーションが始まっていて、ドレイクはこの時長期間イギリスに滞在し、様々なアーティストとの交流を図った。それが今回のイギリスのアーティストの多用に繋がっている。
ドレイクによるMCは「足元をかっさらおうとするお前らにはうんざりだ」というもので、ゴーストライターを雇っているなどといったディスに対応していくやるせなさと同時にどうしてもそれに応じてしまう心情を吐露している。
ジョージャ・スミスが自身のインスタグラムで公開したドレイクとのツーショットはこちら。
5. Get It Together
これはナインティーン85とNoah "40" Shebibというトロント勢のプロデューサーによる強力なトラックで、ハウスとダンスホールをハイブリッドさせたようなビートはまさにイギリス寄りなものだし、そのせいかジョージャの独壇場となったトラックになっている。
しかしこの曲には元ネタがあって、ほとんどが南アフリカのDJであるブラック・コーヒーによる"Superman"が引用されている。歌の内容も元ネタのままで、男女の関係の機微を歌ったものだ。
まさに自分の追求する人間関係ものに見合った曲としてドレイクが今回取り上げたということだろう。というわけで、ドレイク自身はほとんど脇役に回った展開になっていて、しかも甘い歌い手に徹している。
6. Madiba Riddim
これはどこまでもポップなアフリカン・ビートとカリブ・テイストを合わせたような曲で、まさにタイトルすばりの曲だ。
つまり、ネルソン・マンデラの愛称「マディバ」とカリブでのリズムの俗称「リディム」を合わせたタイトルで、ドレイクはこのビートに合わせて誰も信用できない自身の孤独とそれゆえの関係の不可能性を歌っていくが、微妙にアフリカン・ポップスとカリビアンな節回しを織り交ぜながら繰り出していく歌そのものが絶妙過ぎる。
しかも語呂そのものは完全にU.S.で使用される英語になっているというのが究極の聴きやすさになっていて、エンタテイナーとしてのドレイクの才覚をみせつけるものになっている。
7. Blem
これはエレクトロニックなサウンドに、やはりカリブ風のビートが被さってくるトラックによる歌もので、メロドラマ的人間関係もの。
タイトルの「ブレム」は「ハイになる」というような意味で、そうでもしないと自分の本心を相手に伝えられないというニュアンスをかもしつつ、ぶっちゃけた本音も言えない(言ったらそこでおしまい)という、これもまたアンビバレンツというか、どう転んでもどうにもならない状況を歌った曲になっている。
この軽快な南国ムードの中で、一歩も進めなければ引くこともできない蟻地獄的な状況を延々と歌い上げる。
8. 4422
この曲はこれまでの楽曲の甘さを受け継いたエレクトロニック・ビートによるバラードとなっていて、中盤の展開とのブリッジとなっている。
ゆったりしたグルーヴとメロディとの絡みがフランク・オーシャン的で、ドレイクはこの曲についてはサブトラクトやジェシー・ウェア、The XXなどとのコラボレーションで知られるイギリスのサンファに託している。
実際、歌詞からしてサンファにしかこのリアリティを伝えることができないのだ。というのも、何度も繰り返される「4422」とは国際電話におけるイギリスの国番号(44)とシエラレオネの首都フリータウンのエリアコード(22)で、イギリスで育ったサンファがイギリスと両親の出身地との間で引き裂かれる思いを歌っているのだ。
同じように父親がシエラレオネ出身のブラッド・オレンジと共通する文脈がここでは綴られているのだ。こうした離散家族的な情感をドレイクとしてはイギリス特有なものとして注目しているのかもしれない。
9. Gyalchester
ハンガリー出身のiBeatzによるこのトラックで一気にエレクトロニック・ビートに雪崩れ込む。この曲はまさに絶頂を極めている自身の現状をみせつける俺様節で、ここでまたヒップホップ・エッジ全開に。
何をやらせても大成功へと繋がる今の自分の状況を綴りつつ、常に自分を消したがっている輩に見つめられている心境を吐露してみせる。
同時に「今自分を殺したところで、死んだらさらに乗り越えられない存在へと巨大化するはずだ」とうそぶいてみせる内容にもなっている。
タイトルの「ギャルチェスター」とはジャマイカにあるマンチェスターという地区のあだ名で、美女が多いことからそう呼ばれるのと、ダンスホール系のアーティストには男根主義が多いので男を意味する「man」をあらゆる言葉から排除し、「gyal」に置き換えてしまうという言葉遊びから生まれた言葉でもある。
それが転じて、イギリスのマンチェスターをこう呼ぶこともあるのだが、歌詞中には特にこのタイトルに関連したことはなにも登場しない。あるいはツアーでマンチェスターを訪れた際に書いた曲だということなのかもしれない。
10. Skepta Interlude
イギリスのMCであるスケプタと"Passionfruit"にも参加したナナ・ローグスによるトラックで、これもまたまた完全にスケプタに託した曲。
グライム直系のビートとMCが炸裂し、ギャングで薬物取引をしていた過去から、今やシャネルのショーの前列に陣取るようになった現在の自分の成り上がりをみせつけつつ、物欲にこだわらなくなった自分なりの現在のメッセージを伝えることに邁進したいというスケプタ独自のストイシズムも匂わせる内容となっている。
スケプタは「アルバムに関わった全員に敬意を」と自身のインスタグラムで語っている。
11. Portland
ミーゴズのクエヴォ、トラヴィス・スコットという異色のMCふたりを客演に従えたトラックで、どこか呪術的なリフを繰り返すマーダー・ビーツのトラックもサイキックに響き、この顔触れを盛り上げるものになっている。
ドレイク、クエヴォ、トラヴィスの順で繰り出すMCはそれぞれが「いかに他のラッパーと違うオリジナルな表現をやってきたか」「自分のやっていることは誰にも真似させない」という意志を表明する内容になっていてる。
特にドレイクは俳優からMCへと転身したという、通常のコースを辿っていないことについての自負を込めている。
タイトルの「ポートランド」はNBAのポートランド・トレイルブレイザーズの名前をもじってのもの。トレイルブレイザーズとは西部開拓時代に開拓移民の街道となったオレゴン・トレイルを激しく行き来する者という意味で、これをドレイクがもじっているのは「わが道を行く」の意から。
トラヴィス・スコットはポートランドが「アメリカで平和を見つけることができるお気に入りの場所」と自身のTwitterでつぶやいている。
I was once asked my fav place in America to find peace. Portland is the answer. Took a trip and found happynes pic.twitter.com/aYnBwH7D5v
— TRAVIS SCOTT (@trvisXX) 2017年3月17日
後編に続く。
(高見展)







![JAPAN、次号の表紙と中身はこれだ! [Alexandros]/別冊 SUPER BEAVER/King Gnu/THE ORAL CIGARETTES/細美武士/Mrs. GREEN APPLE/back number/Vaundy/マルシィ/ロック花見会](/images/entry/200x200/212029/1)